1秒の定義はどう変わる? セシウムから光学時計へ(背景と候補)
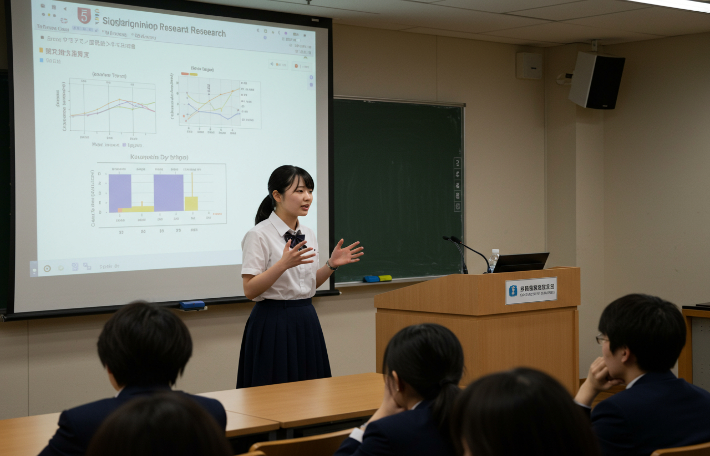
現在の1秒の定義
現在、国際単位系(SI)の「1秒」は、セシウム133原子の基底状態における2つの超微細準位間の遷移に対応する放射の振動数を基準に定められています。 具体的には「9,192,631,770回の振動に要する時間」が1秒です。 この定義は、1967年の国際度量衡総会(BIPM)で正式に採用され、以来半世紀以上にわたり国際的な時間の基盤となってきました。
なぜ見直しが必要なのか
セシウム原子時計は安定で信頼性も高いですが、近年は「光学(オプティカル)原子時計」の開発が進み、セシウム時計をはるかに超える精度を実現しています。 例えば、NIST(米国標準技術研究所)の光学時計は、1億年に1秒程度しか誤差が生じないレベルに到達しています。 このため、世界の計量機関は「より正確な基準」によって1秒を再定義する検討を進めているのです。
今後の有力候補
光学時計の候補には複数の原子・イオンが挙げられています。特に有力とされているのは以下です:
- ストロンチウム光格子時計 — 世界各地で開発が進み、国際比較でも高い安定性を示している
- イッテルビウム光格子時計 — 実験のしやすさや性能のバランスで注目されている
- アルミニウムイオン時計 — 超高精度だが技術的に難易度が高い
これらの候補は、国際的な光学時計ネットワーク比較実験でも検証が進んでおり、複数の候補を並行して評価したうえで、最終的に新しい定義が決定される見込みです。
採用の時期と影響
国際度量衡局(BIPM)は、2030年前後の再定義を目指してロードマップを提示しています。 一般生活に直ちに影響があるわけではありませんが、GPS測位、インターネット通信、金融取引など「ナノ秒単位の正確さ」が求められる分野では恩恵が大きくなります。
まとめ
「1秒」の定義は、私たちの日常生活からは見えにくいですが、社会インフラの基盤として非常に重要です。 セシウムから光学時計への移行は、時間計測技術の進歩を象徴する大きな節目です。 2030年頃に予定される新しい1秒の誕生は、人類の「時のものさし」がさらに精密になる歴史的瞬間といえるでしょう。

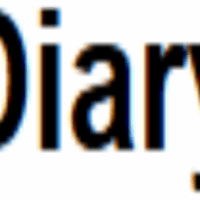
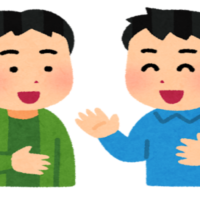

この記事へのコメントはありません。